【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
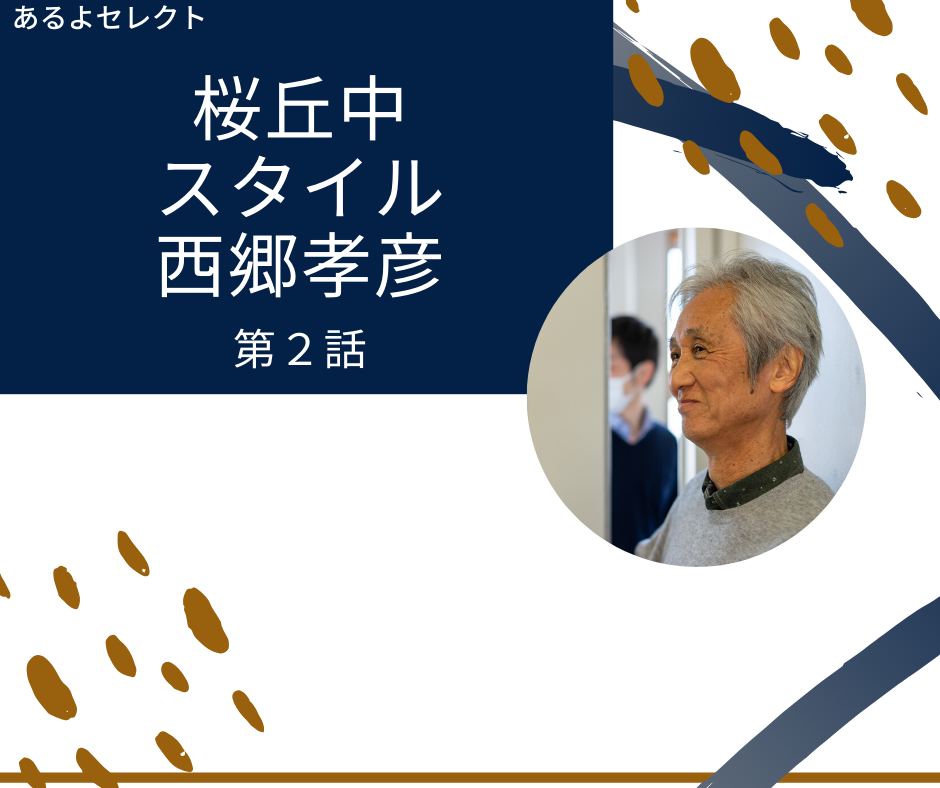
桜丘中学校の校長室は校舎1階、玄関を入ってすぐ、職員室の隣にあります。正面には校長先生の大きなデスク、その前にどっしりした応接セットが置かれています。
「生徒はだいたいこの席に座るんですよ。そこで好きなことをしたり、僕としゃべったり」
そう言って、西郷孝彦校長はデスクの前の一人掛けソファを指しました。
校長室というのは、たいていの中学生にとって滅多なことでは足を踏み入れない、近寄りがたい空間ですが、この学校は少し違うようです。時おり生徒が訪れては校長先生と気軽に会話を交わしていきます。
「先生…」。ノックと共に遠慮がちな声がしました。男子生徒がドアのすき間から顔をのぞかせています。
「おう、どうした?」
「すみません、お客さんなのに。先生、今日はもう帰りますんで」
「もう来ないの? 後でまた来る?」
「はい、部活に」
「そうか、戻ってくるんだね。わかった。じゃあね」
西郷先生が手を振ると、生徒はきちんとお辞儀をして帰って行きました。
「あの子はときどき校長室に遊びに来るんです。今日はお客さんがいるから遠慮したんだね」
桜丘中学校にも不登校の子や教室に入りづらい子がいます。
「それぞれに来られない理由があるんです。そういう子は無理して全部の授業に出なくてもいい。少しの時間でもいいから学校に来られるように、学校にいられるように、できるだけ環境を整えています」
校長室での対応もそうした環境作りの一環です。学校に居場所があること。それで救われる子どもたちが一定数いるのです。
校長室から職員室に続く廊下もそんな居場所のひとつ。窓際に置かれたテーブルでは数人の生徒が思い思いに過ごしていました。読書をしたり、パソコンに向かったり、教科書を開いて勉強している子もいます。
「この子は映画を作っているんですよ。今度、フランスに行くんだよね?」と言って西郷先生が紹介してくれたのは1年生のRくん。朗らかで利発そうな少年です。不登校から復帰してこの廊下で学んでいる生徒の一人です。
「映画を見るのが大好き。今は映画のワークショップに参加しています。中学生だけで映画を撮っているんです」
初対面の私たちに物怖じすることなく、目を輝かせながら説明してくれました。
「授業には出ないの?」
「はい。ここでやることがあるから」
今は3時間目。他の生徒たちは教室で授業を受けています。Rくんは教室には行かないけれど、生き生きした表情から充実した中学生生活を送っていることが伝わってきました。
でも、友達が教室に来なかったり、途中で帰ってしまうことをクラスメートはどう感じているのでしょうか。複雑な思いがあるのでは?
「別に。ふつうですよ」と西郷先生。「関わりが少ないから難しい面もあります。でも、来ればふつうに接しています。なぜなら、その子だけが許されているわけじゃなく、誰もが同じようにして構わないので。朝、来たくない子は来なくていいよ、ってみんなに言っていますから」
大切なのは、子どもたちが中学校での3年間を楽しく過ごすこと。幸せに生きるための方法を知ること。そのためなら前例がないことでも積極的に取り入れるというのが西郷先生の考えです。タブレットにしろ、遅刻の扱いにしろ、困っている生徒の助けになるのなら配慮するのは当然のこと。そして、それは特別な一人のためではなく、誰もが同じように配慮を受けることができる。その姿勢がぶれることはありません。
西郷先生が校長として着任して今年で10年目。いじめや校内暴力が横行していた学校が、今では学区外からも進学を希望する子がいるほどの、区内でもトップクラスの中学校に変わりました。今、桜丘中学校には全国から見学者が後を絶ちません。
「校則がないと荒れるんじゃないか、チャイムが鳴らないと座らないんじゃないか。それを実際に確かめに来るみたい(笑)。でも、こちらもよその学校のことがわかって逆に勉強になります。不登校の子がいたり、発達障害の子がいたり、先生たちの問題もあったり、みんな同じような悩みを抱えているんだなって」
見学者たちのそうした懸念はたいていの場合、校内を見て回るうちに生徒たち自身によって取り払われるようです。校則などのルールがなくても、いや、ルールがないからこそ、自分で考え、自主的に行動する力を身につけた生徒たち。自律する彼らの生き生きとした姿は見ていて気持ちよく、どんな説明よりも説得力があります。
校則の全廃や私服の着用など、前例のないこと、常識をひっくり返す試みを実践するのは容易なことではありません。でも、西郷先生の手にかかると、型破りな取り組みがとても自然なことのように見えてくるから不思議です。
そうは言ってもご苦労も多かったのでは?
「ぼくは9年間やってこれたから。時間がかかることなんでしょうね。最初はたいへんでした」
何がたいへんだったんですか? と重ねて聞くと、「やっぱり先生方の旧来の考えでしょうね」という答えが返ってきました。「どうしてもわかってもらえないときなんか、ここだけの話、諦めかけたこともありました(笑)」
取材の終わりに先生の教育に対する思いを伺いました。
「教育というのは、子どもの心の中を整理することだと思うでしょ。これはこうだ、ってきちんと整えてしまう。でも、それは違う。きちんと整えられ固くなってしまった心を、もう一度ぐちゃぐちゃにしてかき混ぜてあげるのが教育だと思います。
今までの価値観をひっくり返してやる。当たり前だと思っていたことが、本当はぜんぜん違うんだ、ってなったとき、子どもは変わります。自分の知らない世界があることを知る。人はそれぞれ違うこと、そして、自分も人と違っていていいんだということに気づく。そうじゃなきゃいけないって思い込んでいたことがひっくり返るんです」
価値観が多様であることを実感できれば、他の人に寛容になるし、どんなことも自分なりに受け止めることができるようになります。今までの常識を少し超えるだけで新しい視界が開けるかもしれません。
「Enjoy Difference, Enjoy Diversity!」( 違いを楽しもう!多様性を楽しもう!)。
学校紹介のパンフレットにはこんなことばが謳われています。多様な価値観に触れた生徒たちはどんな未来を拓いていくのでしょうか。子どもたちの可能性は大きく広がっていきます。
★現在公開中のあるよストーリーはこちらからご覧いただけます★
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ