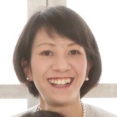教室で子どもたちに教えたいのは、未来に向かって生きる力です。
学びの手段が読み書きですが、脳の機能によって、読み書きそのものに困難を抱える子どもたちがいます。
読み書きが足かせとなって、学びたいのに学べない。
息子もそうした子どもの一人です。
手で書くことが苦しくて、ノートを破り、鉛筆を折って帰ってくる日も。
それでも、学ぶことは好きでした。
タブレットでノートテイクを始めると、可能性が大きく開けました。
中学校では定期テストもPCで受けました。
高校入試も一部の高校をPCで受験しました。
本質的な学びを保障するための、あんな配慮やこんな配慮が、こうした子どもたちの可能性を広げます。
読み書きの、困難の解決は、ここにあります。
勇気を振り絞って、新しいやり方で、学びの扉をたたく子どもたちを、応援してください。
学習障害があっても学べる社会をつくる。
全国どの地域に生まれても、学習に困難を感じる子どもたちに、本質の学びを保障したい。
学習に困難を感じる子どもがいたならば、適切な配慮が速やかに行われ、読み書きのやり方は違っても、一人ひとりの子どもたちが、学びの現場で確実に生きる力を育んで、社会に飛び立っていける。
そんな社会をつくりたい。
文部科学省によれば、学習障害(LD)とは、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである」と定義されています。
担任教員等、学校現場の把握に基づく調査によれば、通常の学級に在籍しこれらの6分野(聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する)の一つ、あるいは複数で、著しい困難を示す子どもの割合は4.5%と言われています。
「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」 平成24年 文部科学省初等中等局特別支援教育課
親の会活動などを通して見ると、学習障害は見る人の経験が乏しいことから、保護者が把握することがなかなか難しく、また現場での実態把握も難しい状況があります。
さらには、保護者・本人・または学校のいずれかで困難の実態を把握できたとしても、その三者のいずれか、または周囲の人々の理解を得られないことにより、配慮が実現できていない現実も見えてきます。
学習障害の実態や、配慮の実際について、広く社会全体で共有できる仕組みを作り、一つの解決に他が学んで新たな解決を増やしていく循環をつくることで、学習障害があっても本質の学びが保障され、
のびのびと自己の学力を伸ばす解決を全国に増やしていくことが、私たちに課されたミッションです。
そのために、私たちは、以下の事業を行っていきます。