【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
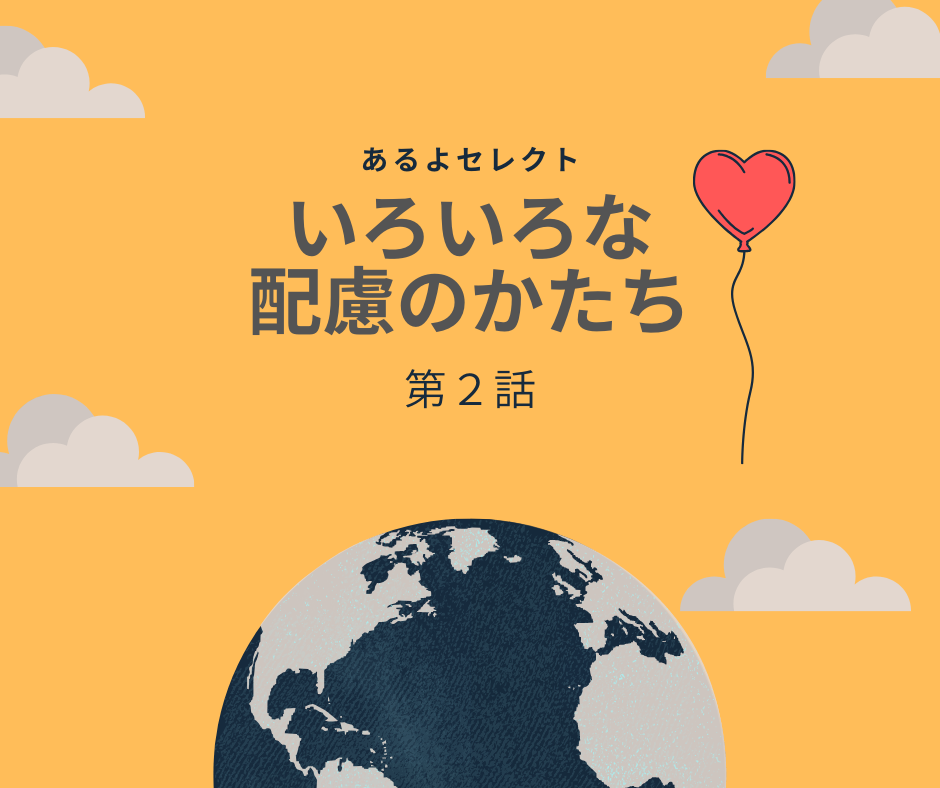
自分を知ること、そして、カミングアウトするということ
今、中学校との関係はいかがですか。
幸子さん いろいろ協力してもらっています。でも、入学前の最初の面談では、校長先生をはじめ先生方が6人も集まってくださったんですが、その中でディスレクシアを知っていたのは、養護教諭だけでした。
中学校や先生とのやりとりで心がけていることはありますか。
幸子さん 学校の立場に立ってみたら、「この子は本当に配慮が必要なのか」という根拠、「配慮をしたらなにか問題が起こるのか、あるいは起こらないのか」っていう情報は絶対必要だと思います。だから、先生がどれだけ不安で、周りとの調整に気を遣っているか、というのをすごく意識して情報を提供するようにしていました。
それから、なにか新しいことをお願いするときは事前に検証するようにしています。拡大コピーひとつとっても、家でいろんな倍率を試して、これだったら意味があるっていうのを確認してから学校に申し込みました。
そのとき必ず付け加えるのが、「これは決定ではなく、また変わるかもしれません。でも、とりあえずやってみていただけませんか」ということ。十分検証しているけれど、家でやるのと学校でやるのは違いますから。他の生徒さんに影響があったり、先生に過度な負担をかけるかもしれない。「絶対にこれで」っていうのは、先生も不安だと思うんです。
お話を伺っていると、先生をとても気遣っていますね。先生へのリスペクトを感じます。
幸子さん 基本的に先生とはけんかしない姿勢なんです(笑)。先生方がたいへんな思いをしていることを知っているから。
配慮を受けるときキーパーソンになるのは校長先生ですが、いちばんたいへんな思いをしているのは現場の先生かもしれません。
幸子さん ある先生に「たいへんですよね」って言ったら、「私、図太いから何を言われても大丈夫よ」って返されたんです。「ああ、言われてるんだな」って思いました。先生方がつらい立場にあるのを知っているからこそ、安易に配慮を求めたくないし、迷惑をかけたくない。できるところは自分でやって、ていねいに進めたいと思っています。

幸子さん
ぼくは、ディスレクシアがあります
幸子さん 中学に入学したばかりの頃、作文を書いたんです。廊下にはってある作文、ありますよね。いちばん最初の保護者会でみんなが見るような。息子はそこで、「ぼくは、ディスレクシアがあります」って書きました。
「小学校ではこんなふうにがんばった。乗り越えなくちゃならないこともあったけど、学ぶ喜びを知ることができた。中学に入り、ぼくがどんな状況なのかみんなに知ってもらわなくちゃいけない。ぼくには転機が3回あった。これが、新たな転機である。」
すごいですね。決意表明というか、覚悟のようなものを感じます。
幸子さん 中学校で配慮を受けるうえで、ディスレクシアがあることを本人が受容できていたのは大きかったと思います。少しずつですが、小学校の段階でカミングアウトできる自分になっていたこと。とことん努力して、できない自分を認められていたこと。どちらも息子にとって必要なことでした。うちは主人も私もパソコンを使うので、小学校1年のときから息子に「使いなさい」ってタブレットをポーンと渡すような家だったんです。でも、息子が、「ぼくは書きたい。みんなと同じがいい」って。子どもにはそういう時期があるでしょう? だから、「みんなと同じがいい」にとことんつきあうことにしたんです。
自分の限界を知る。そして受け入れる。
「自分はどのくらいできるんだろう」っていう自分探しでもあるんですよね。何がどのくらいできるのか、それともできないのか、自分でもわかっていないから。
幸子さん 「もしかしたらぼくは努力していないのかもしれない。だから最大限がんばる」って言って、本当に死に物狂いの努力をしました。はじめは10問テストで100点取るところから。それを命をかけるくらいの勢いでやったんです。でも4年生くらいになると、量が多くなったり問題が変わったりしてだんだん苦しくなってきた。そんなとき、200問テストにチャレンジ、っていうのがあったんです。
200問? 100問でもたいへんなのに。
幸子さん 息子は「がんばりたい」と言ってものすごい努力をしていました。だけど、「80点以上取らなくちゃいけないんだ」って思ったら、こわくなっちゃったんですね。結局、テスト当日には受けられませんでした。並行して文字を書く練習も続けていました。寝る間も惜しんで努力して努力して。でも、あるとき、「もう苦しい」って。そこまでしてやっと、「ぼくは書けない」っていうことに気づいたんです。
つらいですね。でも、限界を知るのは大切だし、書けないということに自分で気づくプロセスはあった方がいい。
幸子さん そうなんです。それまで、いくらタブレットを勧めても「うん」と言わなかったのが、「やる」って言うようになりました。きっとそのときには「やりきった感」があったんだと思います。
とことん努力したうえで、「もう無理だ。自分の限界はここだ」というのを知って配慮を求めるのは、訴え方というか、切実さの度合いが違いますよね。
幸子さん 本人の納得感も違いました。「こんなに努力して漢字を練習しても忘れちゃう」。しかも、作文で書こうと思ったときに出てこない。「結局は書けないじゃん」ってなったときに、「じゃ、パソコンを使ってもいいんじゃない?」ってなりました。
はじめは、ぼくがいないところで
小学校で自分と向き合った体験が中学での前向きな姿勢につながっていますね。
幸子さん 心の準備というか、そうした葛藤を10歳の壁までに体験できたのはよかったかもしれません。もうひとつ、ディスレクシアをカミングアウトしたことも彼の中では重要でした。息子は3年生の秋から通級に行き始めたんですが、そのときはみんなに内緒にしたがったんです。不安だったんでしょうね。でも、「なんで先に帰るんですか」って聞かれることがストレスになって、「カミングアウトしよう」っていうことになりました。
LDの子が主人公の『ありがとう、フォルカーせんせい』っていう絵本があるんですが、息子が通級に行ってる間、その本を先生がクラスで読んでくれました。そうやって、まずクラスメイトにカミングアウトしたんです。
3年生でカミングアウト? すごいですね。
幸子さん でも5年生に上がるとクラス替えがあるでしょう? するとまた「なんでひとりだけ違うの?」ってなるわけです。今度は私が『どんなかんじかなあ』と『りゆうがあります』という絵本を読みました。それで「息子には理由があります。あなたにも理由があるでしょう? どんなかんじかなあ。想像してね」という話をして、改めてカミングアウトしました。
そのとき息子さんは?
幸子さん 一緒に聞いていました。「3年生のときはぼくが通級でいない間に読んでもらったけど、今度はぼくがいるところで読んで。ぼくがいる前でみんなにぼくの特性を説明して」って息子に言われたんです。カミングアウトするときに自分もその場にいるということを5年生で体験できたのはとても意味がありました。
「ぼくがいないところでみんなが知る」、「ぼくがいるところでみんなが知る」。そういうステップを踏んでいたから、中学生になったとき、作文という形で、「みんなの前でぼくが自分で伝える」ということができたんだと思います。
いろんなことが全部つながっているんですね。
次回は、「しない配慮」もある です。1月30日公開です。
★現在公開中のあるよストーリーはこちらからご覧いただけます★
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ