【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
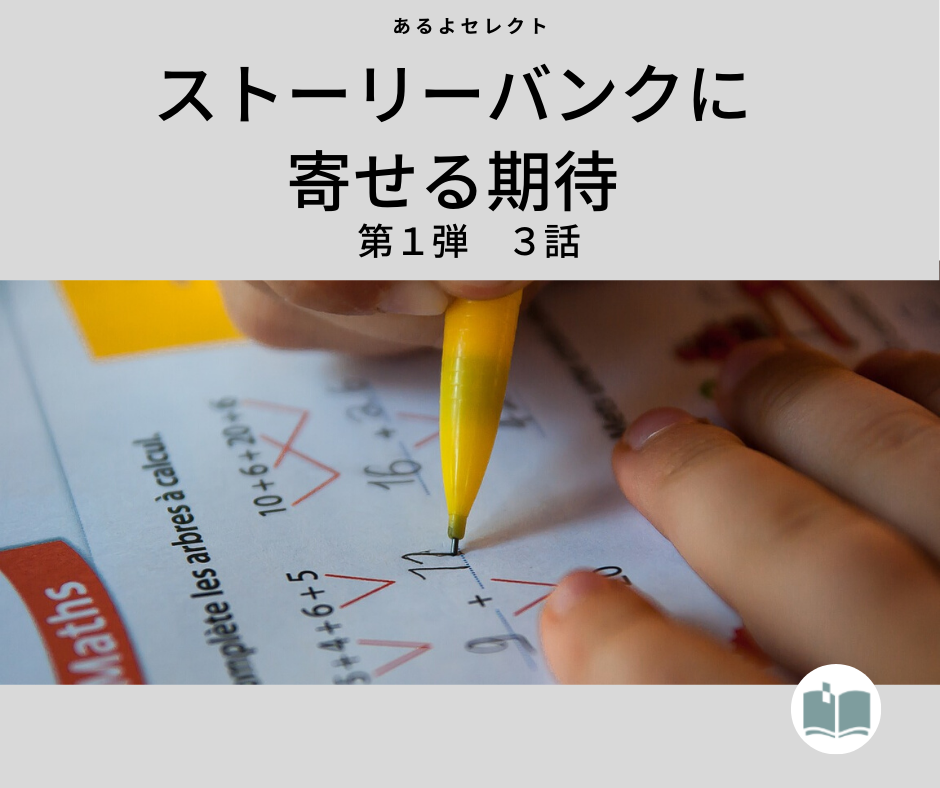
事例を共有することで見えてくることがある
2018年6月24日、文部科学省初等中等教育局 特別支援教育調査官 田中裕一様と、理事の武井が対談しました。特別支援のスペシャリストである田中様に、読み書きに困難を抱える子どもたちを取り巻く課題と支援のあり方についてお聞きしてきました。
最終回の今回は、当事者中心の合理的配慮の実現について、具体的にお話をお聞きしています。
武井 子どもが困っていることに気づいたとき、合理的配慮を実現しつなげていくために、保護者と学校との関係はどうあるべきでしょうか。どうすればうまくいくと思われますか。
田中 どのようにして話し合いをうまくやるかが大切ですよね。僕のところにはいい事例も悪い事例もたくさん入ってくるのですが、「これがないとうまくいかないよな」というのが、相手に対しての尊敬、 相手がやっていることに対するリスペクトです。
先生に対しては、「いつもありがとうございます。他のところは今のままでいいのですが、この部分だ けなんとかなりませんか」、保護者に対しては「がんばってますね。でも、もうちょっとここ、一緒にうまくやれんかな」、というような相談の仕方。いろいろ言いたいことがあっても全面否定はせずに、お互 い相手を尊重することができたら、そんなに困らないんじゃないかな。
武井 困るのは建設的な話し合いができなくなることですよね。
田中 そうなったら損をするのは子どもなので。それは避けたいですから、大人同士、相手をリスペクトしながら話し合いができる関係を築いていくのが大事なんじゃないかな。保護者も先生もいろんな人 がいますから画一的な方法はないと思うんです。ただ、お父さんは、お母さんは、どういうことを考え てどういういことを子どもに望んでるのかというのを想像する。僕なんかは、相手によって(説明や対 応を)変えたりもします。
だけど、やっぱり本人がやりたいと思わなければ話にならないと思うんですよ。どんな子もそうなんですけど、特に発達障害の場合、本人をほったらかして話をしてもうまくいかない。
よくあるんですよ、保護者と学校側で一生懸命、指導計画をつくって、「さあ、やろう」って本人に提案したら、ちゃぶ台返し、バーン!! みたいな(笑)。
武井 わたしも失敗したクチです(笑)。 本人を置いてけぼりで、先生と保護者だけで話をすすめてしまったりというのは意外にやりがちですよね。
田中 本人抜きの将来設計なんて、その子が望んでなければやっぱりうまくいかない。本人が参加する、 本人と共有するというのが重要です。子どもって、小さいときは保護者と以心伝心かもしれないけれど、 小学校高学年になって精神的にも発達してくると、自分が「いいな」と思っていても「親がいいって言 うからイヤ!」ってなるわけでしょ。ですから、本人が「こうやりたい」ということに対して、親が「じ ゃあ、わかった」というやり方をどこかでしていく必要がある。最後の最後まで保護者が指示したこと に子どもが「はい」と答えるだけの状況だと、たぶん子どもの成長という面でもあまりよくないんじゃ ないかな、と思います。
武井 本人が関わることが大切ですね。
田中 やっぱり、本人と保護者と学校というのは、一体のものだと思うんです。そのうえで話し合いを進めるのが大事。そして、もうひとつ考えておきたいのは周りのことです。
実は内閣府が去年行った調査で、合理的配慮について知っている人は全体の2割という結果が出たんです。
これは、関わっている人以外はほとんど知らないということ。
「この子に合理的配慮をしましょう」と言ったときに、周りの8割は「合理的配慮って何?なんであの子にだけ特別なことせなあかんの」と思うわけです。それじゃやりにくいですよ。
ですから、障害のある人はもちろんですが、障害のない人、配慮を求めない人にも合理的配慮の事例 を知ってほしいと思います。例えば受験の配慮でパソコンを使う子に対して周りの友達が、「いいよ、お まえはパソコン使えよ。だってそういう話がデータにのっとったぜ。でも、おれは紙で受ける」という ようになったらいいですよね。
武井 教室で隣に配慮を受けている子がいても「ああ、この子はそうなんだ」とみんなが当然なことと して受け止められるような状況が理想ですね。このデータベースがそうした流れのきっかけになれば、 と思います。
田中 合理的配慮は先生が知っておくべき情報ですし、こうしたデータベースによってそれが広まると いいと思います。ただ本来、合理的配慮は子どもの教育権を保障するための当然の配慮として学校がや らなくちゃいけないことなんです。合理的配慮と言われるまでもなく、「子どもの学びを最大限にするた めにはふだんの学びからこういう手立てがいります。受験のときはこういうやり方をしないとこの子は 本領を発揮できません。だからそのための準備を整えているんです」ということです。合理的配慮とい う前に教育的に必要な手立て、支援としてやっています、というのも当然「あり」なんです。
大切なのは、障害のあるなしに関わらず、子どもが本来もっている力を発揮するために何ができるの か。なかなか一筋縄ではいきませんが、みんなで考えていくことが必要だと思います。
武井 子どもを真ん中に、親も先生も一緒になって考えたいですね。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ