【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
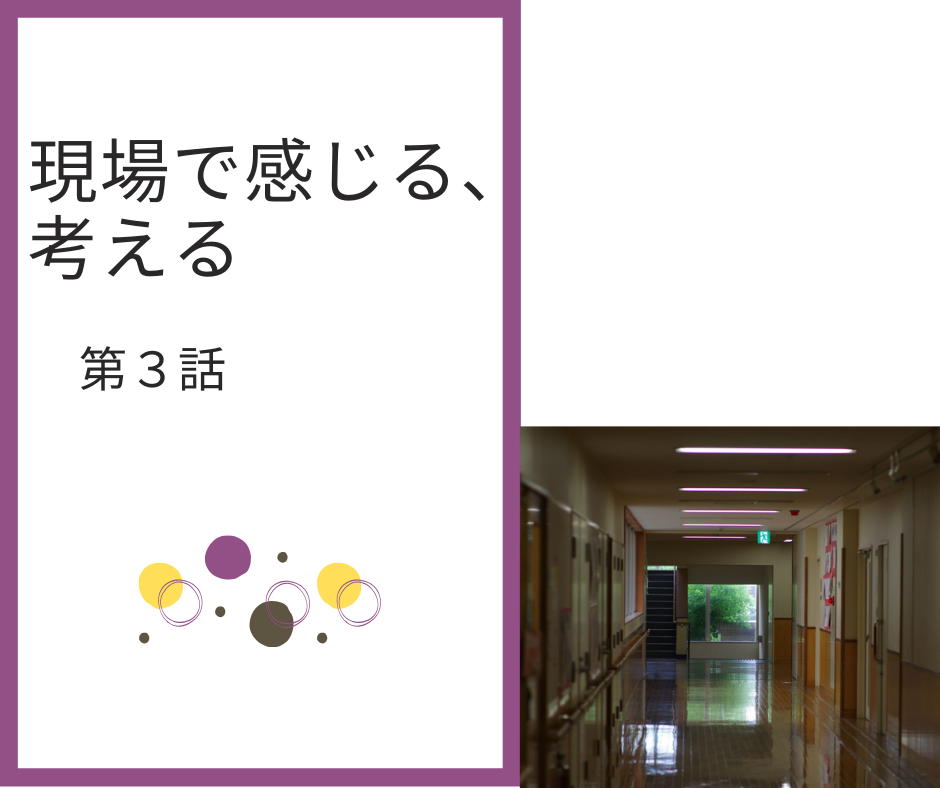
菊田 保護者の方とはどのように話を進められましたか?
鈴木先生 保護者の方とはコミュニケーションが大事ですね。そこがうまくいかないとやっぱり難しいです。

菊田 先生と保護者の意思疎通ですね。できないことも多いということでしょうか?
鈴木先生 お子さんに障害があるかもしれないということをわかっていても認めるまでに時間がかかることは多いです。それでも、やっぱりできないという事実に悩んでしまう。
菊田 そういうのを「障害受容」というんですけど、親の障害受容はすごく難しいです。でも、そこに時間がかかってしまうと子どもへの支援が先延ばしになってしまう。
鈴木先生 保護者の方は話していくうちに少しずつ前向きになられることが多いです。診断してちゃんとしなきゃ、ということで受診もして。それで診断結果が出て初めて少し納得できて、「じゃあ、これからどうしようか」ということを話せるようになっていく。
菊田 病院での診断に限らず、簡単なスクリーニングテストでもいいので、早く状況を把握することが大切ですよね。LDの傾向があることがわかれば、障害を補填するためのアクションを起こせる。障害の診断が出る前でもいいんです。そうすることによって、もしかしたら学校に足が向くかもしれないし、勉強しようっていう意欲がわいてくるかもしれない。
鈴木先生 そうなんです。できないからって必ずしも障害ではないし、その判断は私たち教師にはできない。授業をやっているなかで「もしかしたら」って思う生徒がいても、裏付けが全くないとその状況で配慮を進めるのはとても難しいんです。
菊田 Aくんは高校受験もされてますよね。どうでしたか?
鈴木先生 難しかったですね。本人は情報の方へ進むことを希望していて、志望校の見学にも何度か行ったんですが、どうしてもペーパーテストが厳しかった。それで、私も高校について行って、「中学校ではこういうふうに授業でパソコンを使っています」ということをアピールしておこうと思ったんです。
菊田 それはとっても大事です。
鈴木先生 ただ、受験の形態を変えてもらうとか、そういうところまではできないと思っていましたし、そこまでやってしまうと彼の場合、逆によくないな、と思っていました。
菊田 それはどうしてですか?
鈴木先生 その頃までにAくんはだんだん書けるようになってきてたんです。パソコンを使うようになって書くことに自信がついてきた。だから、他のこともけっこう伸びてきたんですよ。
菊田 ああ! 表出の回路ができてくるから書けるようになる、って息子も言ってました。書く能力って本当に上がっていくんですよね。
鈴木先生 そうなんです。いい方に回ったんだと思います。字が違ってきたんです。今まで、これは読めないだろうっていう字だったのが、けっこう読めるようになって、ふつうにまっすぐ書けるようになってきて。
菊田 すごーい!
鈴木先生 ああ、よかったな、と思いました。本人もそれでがんばるというので、受験はふつうに受けることにしたんです。自分でやるしかない、がんばるしかない、って言ってがんばってました。たいへんでしたけど、それまでやってきたことと進みたい道がけっこうリンクして、最終的には推薦で入ることができました。
菊田 よかったですね! じゃあ、今は高校でパソコンを使っているんですか?
鈴木先生 高校への申し送りはしたんですが、授業では全部は使っていないと思います。でも、学校側もいろいろとケアをしてくれて、そんなに苦労していないようです。
菊田 本当にすばらしいですね。先生が説明会にも一緒に行ってくださってAくんは心強かったと思います。ですが、正直なところ、先生のご負担は大きいですよね。
鈴木先生 そうですね。そう感じる人もいるかもしれません。私の場合は、自分がやりたいだけで(笑)。感情移入してしまう方で、悔しかったんです、そいつができなかったのが。何かにすごく悩んで、人とぶつかって苦しんで、っていうのを3年間も見ていましたから、もうさすがに(笑)。
でも、同じことを教員全員にやれ、というのは無理ですし、強要することはできません。
菊田 いろいろと難しいですよね。生徒ひとりひとりに向き合って個別対応するのが理想ですが、そうすると教員の負担は増えていく。対応に時間を取られて授業準備もできない。
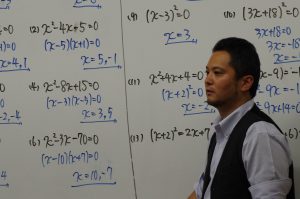
鈴木先生 私は「授業準備なんかは後で自分でやればいい」って考える方なんですが、そうじゃない人もいる。それぞれ事情も違いますし、教員全員にそれを求めるのは無理だと思うんです。だから外部からの支援とか協力があったらいいですね。
でも、「個別に見る」ということに関しては、障害があるとか適応に問題があるとか、そういう生徒だけじゃなくて、ふつうの学習でも同じなんです。どこができてないのか、何が苦手なのか、とか。ひとりひとり個別に見るのが理想的なんですけど、難しいですね。
菊田 アメリカだと成績下位20%層に対して、何ができないか、なぜできないかということを調べるのは教員側の責務なんだそうです。やっぱりそこに着眼するのは大切ですよね。どうしてこの子はできないんだろう、っていう。
鈴木先生 正直、生徒が勉強ができないのは教員の責任だと思うんです。理解させてなんぼ、ですから。いろいろな考え方があるでしょうけど、私は、授業を理解してもらえるように教員が何かやるというのが当然だと思っています。
菊田 それには個のニーズをすくいあげるというのが重要ですよね。やっぱり教室で一緒に過ごしたり授業で教えていると、「この子にはこういうニーズがあるな」というのが一目瞭然にわかるものなんですか?
鈴木先生 いえ、一目瞭然っていうわけには(笑)。
菊田 やっぱりある程度意識しないとすくいあげるのは難しい?
鈴木先生 そうですね。なにか問題がありそうだと思っても、原因がどこにあるのかわからないことがほとんどなので、探り探り…。見つかったらラッキー、くらいな感じです。
常日頃の授業もそうなんですが、子どもたちの行動だったりことばだったりを、その裏に何かあるっていうのをきちんと見ておかないと、その場のイベント的な感じで終わってしまいます。なので、「なんでこんなことを言ってきたんだろう」というようなことは常に考えるようにしています。
菊田 それを30人、40人に対してやるのはたいへんですよね。
鈴木先生 いや、楽しいですよ。子どもたちと一緒にいろいろやっているのが好きなんです。
菊田 やっぱり子どもたちに寄り添って、上手に実態把握をしてらっしゃいますね。先生が子どもをよく見ているかどうかは、保護者にもわかりますよ。何かのときに「その一言がすごい」っていう一言をかけられる先生。「今、それを言ってほしかったんです!」っていう一言を言える人。そういう人が人を育てていくんだと思います。
鈴木先生 そこを目指したいですよね。
菊田 息子がお世話になった先生の話をしていいですか? 子どもたちをよく見ていて、個のニーズを拾い上げるのがとっても上手なんです。息子は身辺整理が苦手で、しょっちゅう鍵を無くすんですが、「先生、家の鍵がありません」って言いに行くと、「また無いの?」って言いながら一緒に校内をぐるぐる探してくれる。それで見つかると、「わかった? これが人生っていうものよ!」って言うんですって(笑)。そうすると帰ってきて息子が、「今日も鍵を探したんだけど、鍵を探すのが人生だって言われた」って言うわけです(笑)。
鈴木先生 最高ですね(笑)。
菊田 だから私も、「それが人生っていうものよ!」って言うわけ。なんかすてきでしょ。
できないこと、やってしまったことはしょうがない。それをいかにしのいでいくか、どう乗り越えていくか、というのがやっぱり人生だと思うんです。
鈴木先生そうですね。難しいことはたくさんありますが、教員もチャレンジしていいんじゃないですかね。それで生徒本人が楽しくなったら、やる気も起きるじゃないですか。だから私も、失敗してもいいから突っ走ってみようかな、そういう感じでやってます。
★現在公開中のあるよストーリーはこちらからご覧いただけます★
次回のあるよセレクトは、7月20日公開です。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ