【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
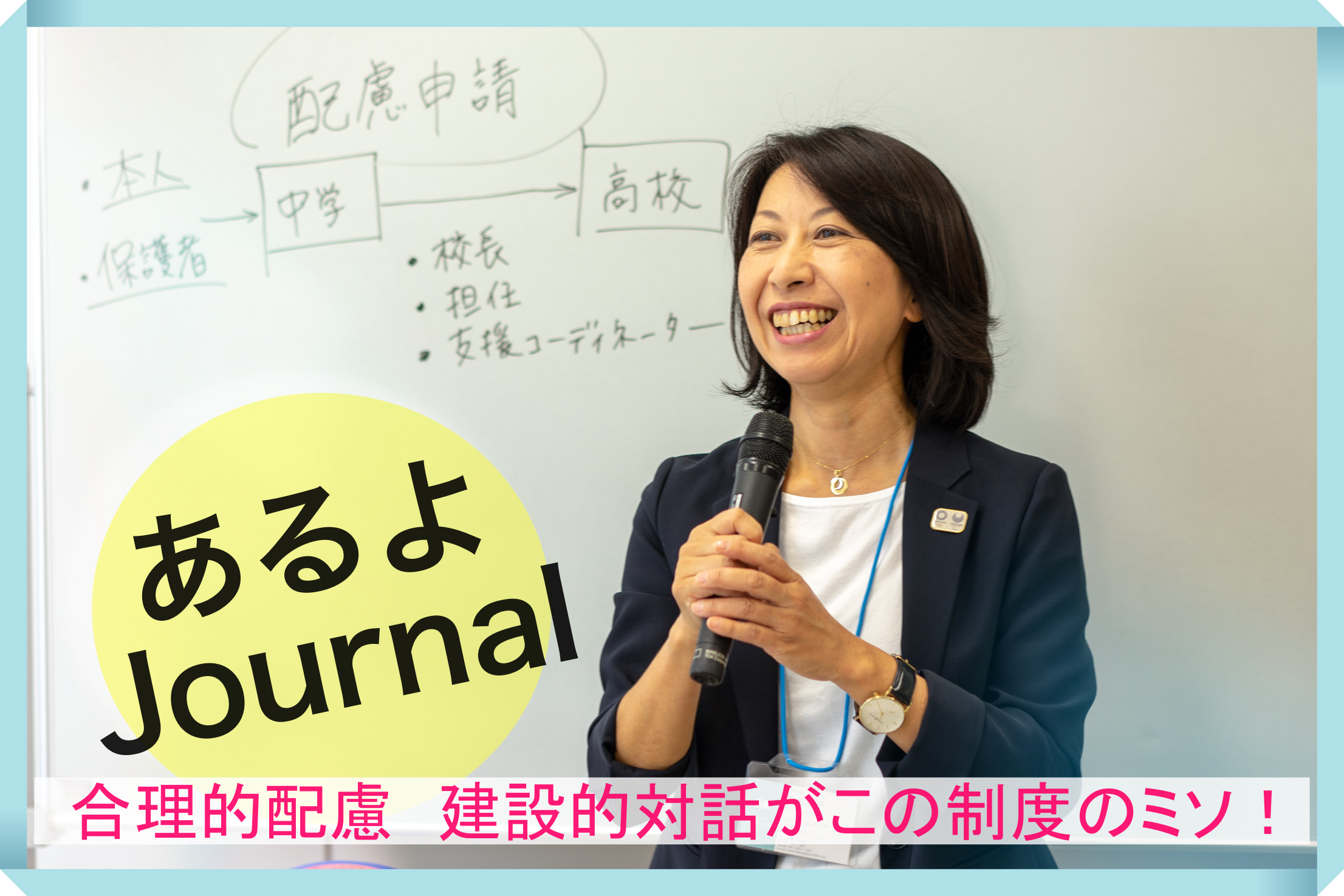
「合理的配慮」と言う言葉を知っていても、うまく配慮にむすびつかないというケースをよく耳にすることがあります。
平成26年に批准された「障害者の権利に関する条約」は障害のある人もない人も共に生きる共生社会の形成に向け、教育面においては障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ「インクルーシブ教育」の理念を提唱しています。
これを受け、平成28年4月1日より施行された障害者差別解消法は、障害を理由とする差別的取り扱いを禁止し、「合理的配慮」を求める意思の表明があった場合には、その提供が国・地方公共団体においては法的義務に、民間事業者においては努力義務となりました。
「合理的配慮」とは、平たく言えば、提供者側に均衡を失した、または過度な負担の無い限り、障害を起因とする困難に合わせてやり方を個別に少し変えましょうという制度です。
過度な負担のない限りで、その人に合わせてやり方の変更を模索する場合、提供者と被提供者の間で、配慮に向けたすりあわせ(建設的な話し合い)は不可欠です。
例えば、通常の学級において、鉛筆でノートを取ることが一般的なスタイルならば、書字に困難を持つお子さんにPCでノートテイクしてもいいよとその子のやり方を少し変えることは、「合理的配慮」にあたります。
この場合、その配慮の実行までに本人・保護者と学校との間で、そのお子さんにあったやり方は何なのか模索するすり合わせが不可欠です。
このプロセスは、実態把握から配慮の実施に至るまでの、これまでの過程と、実は何ら変わりがありません。
被提供者も法律を傘に着るのではなく、提供者側も法律を恐れるのではなく、そのお子さんの実態把握に基づいて、生きる力を育むために必要な配慮はどんなことなのかを一緒になって探る話し合いの過程(建設的対話)こそが、この「合理的配慮」のミソと言えます。
学校の通常の生活における配慮にしても、定期試験の配慮にしても、はたまた受験の配慮にしても、双方が胸筋を開いて忌憚のない話し合いを重ねられると良いですね。
※東京都では、2018年10月1日より「障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行され、民間事業者も合理的配慮の提供が義務とされました。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ