【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
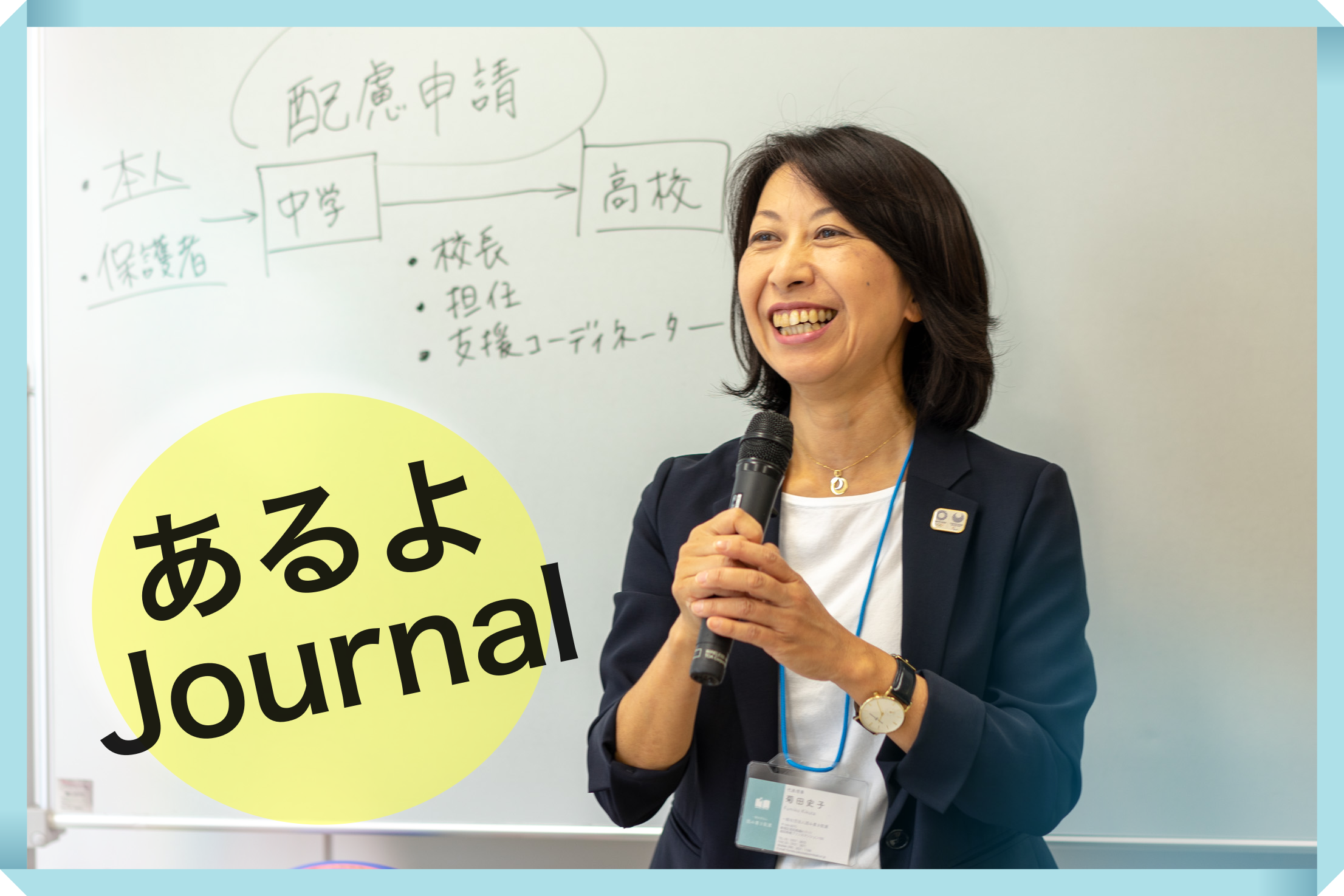
合理的配慮 〜一番たいせつなことは本人の意思〜
「合理的配慮」とは、障害者差別解消法により義務づけられた制度で、障害のある人から意思の表明があった場合に、均衡を失し、または過度の負担のない限り、その社会的障壁を除去するべく配慮することです。
大雑把に言えば、「障害からくる困難の状況に合わせて、やり方を少し変えましょう」という制度です。
例えば、学校においては、通常の学級において、読み・書きに困難のあるお子さんの状況に合わせて、そのお子さんの宿題のやり方を少し変えましょうとか、ノートテイクのやり方を変えましょうといった場合がそれにあたります。
一口に「合理的配慮」と言いますが、支援する大人が忘れがちになる、大事な点があります。
それは、配慮を求めたいと、本人の意思が固まっているかどうかという点です。
読み書きの対する配慮の場合、その配慮の多くは、周りから見える配慮です。
例えば、ノートを拡大する、教科書を拡大する、板書を写真に写す、ノートテイクにPC
を使う・・・。
本人が求めてもいないのに、こうした配慮をすることは、彼らの自己肯定感を下げることになりかねません。
親は特に、つい先走って子どもに配慮を与えたくなります。
大事な子どもが苦労するのを見ていられない。その気持ちは痛いほどわかります。
でも、自己肯定感を下げてしまうことはもっと辛い。
自分が好きというキモチこそ、この社会を生き抜いて行くための原動力だからです。
育てるべき力は、この社会の中で自力で生き抜いて行く力。
自分の得意・不得意を含めて特性を理解し、なおかつ自分が好きという気持ちをもって、こんなヘルプがればボク(ワタシ)はやっていける!と自覚して、周囲にちゃんと説明しヘルプを求めていける力を養うこと。
その力を育て引き出して行くのが家庭であり、学校です。
合理的配慮のスタートは、お子さんが、自分には「〜の配慮」が必要との自覚ができて、願わくばその意思の表明ができるようになってから。(※意思の表明への教育的な配慮については、また別の回で話します。)
得てしてこの子たちは、マイナスの思考に陥りやすい特性があることも理解しながら、配慮を得たいと子どもの意思が固まるまで、支援する大人は気長に寄り添い、辛抱強く待つことも大事です。
先生と保護者がお子さんを中心に建設的な対話を重ね、お子さんのために協力しながら、一緒になってその力を養っていけるといいですね。
菊田のあるよJournal 今後の掲載予定は…
合理的配慮〜公平性とは何か〜
合理的配慮〜一応確認!法的根拠〜
合理的配慮〜建設的対話こそこの制度のミソ!〜
です。お楽しみにお待ちください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ