【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
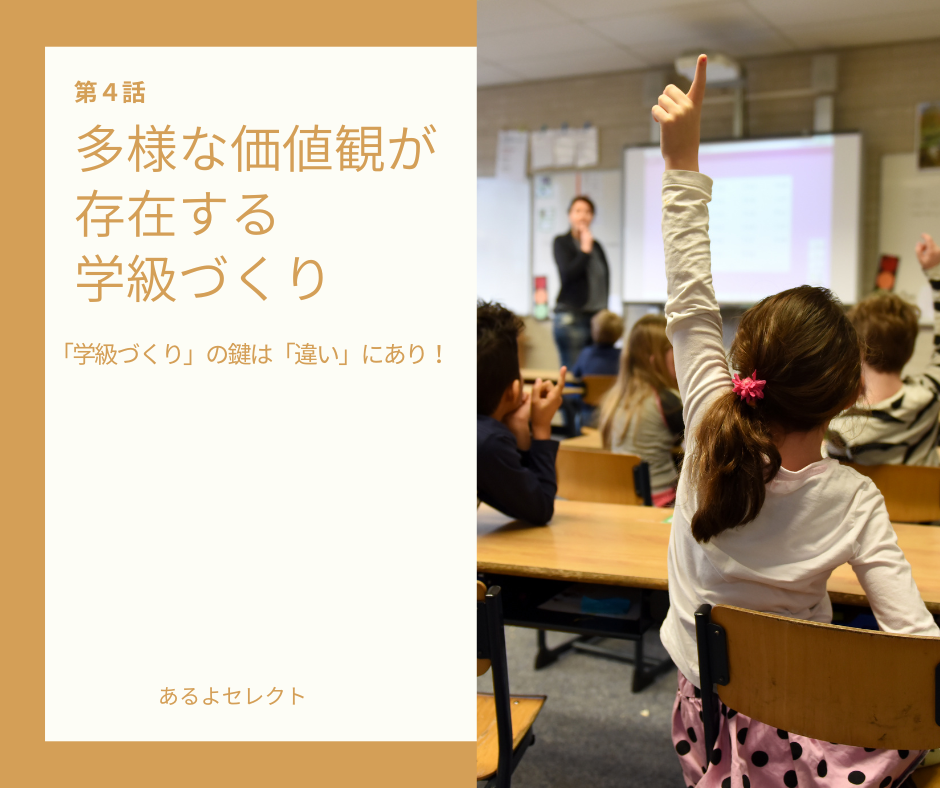
_「学級づくり」の仕掛け② 個々の自尊感情を高める取り組み
先生は自尊感情に着目しておられるそうですが?—-
自尊感情に関しては様々な視点がありますが、私は以下の4つの視点で捉えています。
・自分自身に肯定的な感情をもつこと。
・自分を価値ある存在だと思うこと。
・自分が好きだと感じること。
・自己有用感で高まる。
自己の自尊感情を高めることによって、実は相手を理解し、大事にすることができるようになります。つまり、自分と同時に他者を肯定的にとらえることができるようになるわけです。
他者理解を重ね、人は豊かな人間関係を築いていきます。そしてそれは、全ての活動の「意欲」のもととなります。さらには、異なった価値観をもつ相手に対して、寛容な受容的態度がとれるようになっていきます。
発達障害をもっている子どもの中には、自尊感情が非常に低い子どもがいます。日本では、発達障害がある子どものみならず、全体に自尊感情が低い傾向があります。自尊感情を育む活動は、日本社会に課せられた大きな課題です。
自尊感情を高める取り組みを教えてください—-
学級会以外にも、自尊感情を高めるさまざまな活動があります。その中で特におすすめな「いいところみつけ」を紹介しましょう。低学年からやっていくのが良いです。学級の子ども達のいいところを、子ども達同士で見つけ合い、紙に書いていきます。子ども達は、最初は何を書いたらいいかわからないと言いますが、積み重ねれば積み重ねるほど、いいところを書けるようになっていきます。書いたところが次の子に見えないように、紙を折りながら回して、最終的には折られた紙が、自分のところに回ってくる仕掛けも良いです。開ける瞬間がとってもドキドキするけれど、その瞬間がうれしい。それは低学年でも高学年でも同じです。そうして、読んだら子どもは本当にいい顔をするんです。こんな感想がありました。「自分のいいところがわかって今日は、ほんとうにうれしかったです。もっといいところをふやせるようにこれからもがんばりたいです。またやりたいと思いました。」
「ぼくは、今日のべん強をして、いろんな友だちのいいところを見つけれたし自分のいいところをしってもらえてうれしかったです。またやりたいです。」 私は校内研修の最後に先生方にも「いいところみつけ」をやることがあります。教師にも実感を持ってもらい、そして自己の自尊感情を高められるように。研修が終わった後、「大人だから、なかなかそういうことを言ってもらえる機会がないのでよかった」という感想が出ることもあります。
他にもおすすめの活動はありますか?—
「グループワークトレーニング」も良いです。その中の一つで、1つのケーキをデコレーションするという課題です。予算は決まっており、トッピングにさまざまなものが選べます。しかし、トッピングを全部使うと予算に収まらない。”ではどれを採用するか”を話し合って決めていきます。ポイントは、絶対に多数決にしないということ。そうすると、子ども達は話し合いの中で、「おりあい」をつけるという経験をするんです。今の子ども達は、群れて遊ぶことが少ないので、おりあいがなかなか付けられない傾向があります。じゃんけんはできる。しかし、逆に言えばじゃんけんしかできない。順番に意見を採用することや、半分ずつ意見を取り入れる、新しい方法を見出すなどの方法が身についていないんです。「おりあいをつける」ということを子ども達に経験させることで、自尊感情が育まれていきます。
「学級づくり」の仕掛け③ 活動の目的を明確にして「振り返る」
こうした活動を進める上でのポイントはありますか?—-
目的を明確に押さえて、指導することです。この活動の目的は「違い」が分かる集団につなげていくことです。中にはただ“楽しい”活動としてスキルを真似しようとする教員もいますが、それでは意味がありません。
「違い」が分かる集団につなげるという目的のためには、絶対にやらなければならないことがあるんです。それは「振り返り」です。
この取り組みで、特に押さえたいポイントは「人の話を聞く」「自分の思いを言う」ことです。さらには、「分担ができるようになること」や、高学年になると、「自然にリーダーが生まれてくること」なんです。このポイントを活動の後で確認するのが「振り返り」の機会になります。グループ活動では、「役割分担」が不可欠です。「協力」とは単に友達と力を合わせることだけではありません。一歩踏み込んで、実は「聞く」「話す」「役割分担する」こと。これが「協力」なのだということを子ども達に伝えたいですね。ですから、活動が終わった後の「振り返り」にこそ、意味があるんです。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ