【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
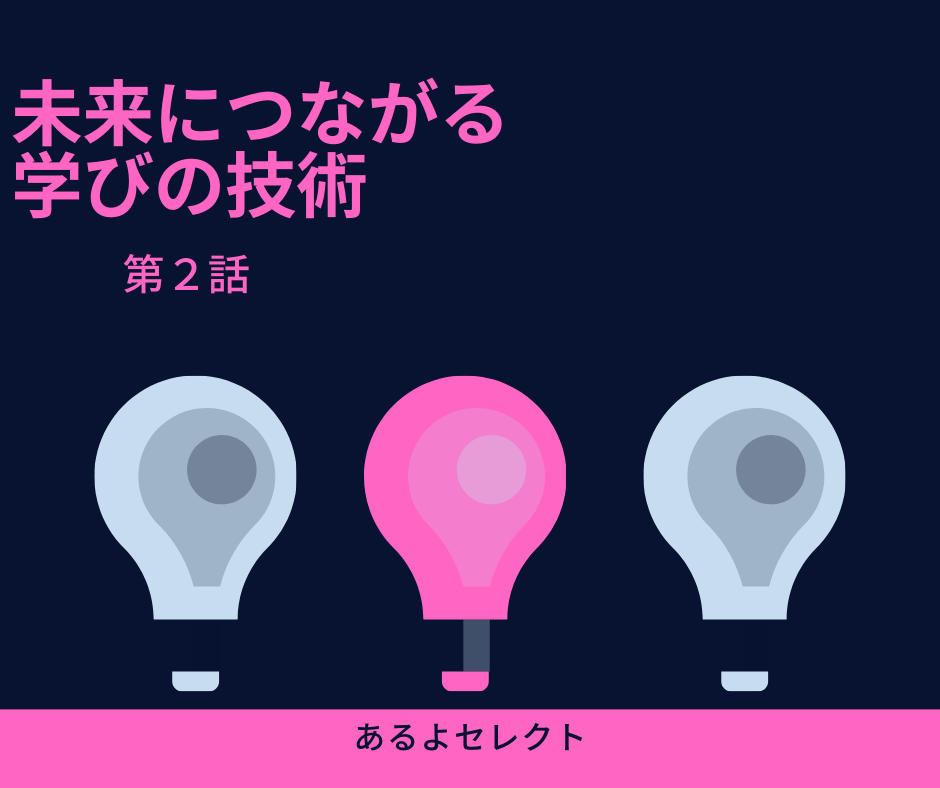
佐藤 ブリキでは、まず最初にお申し込みいただいて、アセスメントを受けていただくんですね。これがURAWSSというもので、読み書きの正確さとかスピードですね、それが同学年のお子さんに対して、「どんな状態にあるのか?」を確認します。その結果として、どんなところに課題がありそうだ、というのが出てきます。
A判定が一番良いのですが、オールAであっても課題がある、とい感じられる子がいます。
菊田 えっ!一番いい判定なのに、どうしてですか?
佐藤 これはなぜかと言うと、求められるのがもっと高い時です。
進学校の子とかに意外といるんですよ。例えば、今小学校4年生なんだけど、その子がやっているのは中学1年生のところまで先行して進んでいる、進学校なので受験に対する勉強と主とする進め方をしているとします。そうすると、その子は通常の小学4年生の子に比較したらAなんだけど、周りの子たちがもっと先に行っているので、6年生とかのレベルあるいは中学1年生のレベルを求められています。それがいいのかどうかはともかく、その子が今いる環境においては「Aであっても課題がある」ということになります。
菊田 環境によって困難さが違ってくるということですね。
佐藤 その時には、正直言って迷いますね。
通常の学校にいれば、この子は問題がないんだけど、環境がもっとスピードとかを求めているから、残念ながら「その中では自分は遅い」と感じてしまいます。「このまま続けると潰れてしまいそうだ」であれば、「私学でも、もう少しおっとりしたペースで進めるところを選ぶ」というやり方もあるし、公立に転籍するというやり方もあります。
そうではなくて、理解はとても出来ていて、書くのが追いつかない、本人も今の流れに乗っていきたい、と思うのであれば、タイピングのスピードをあげるしかないので、「がんばろうか!」という風に進める時もあります。
こうして「それぞれの課題感はなにか」を見立てた上で、そのあと授業に入っていきます。
その時に、個別なのか、小集団なのかに大きく分かれてきます。
基本的には小集団ですね。ですが、それまで失敗体験がとても多かったり、コミュニケーション面があまり得意でなくて「集団に入る」ということに抵抗が強いとか、あるいは他の子とニーズがものすごく違う、という場合には、個別にさせていただくことが多いです。
そして、推奨年齢は小学校4年生から中学校1年生ぐらいまでなのですが、実際には小学校1年生から大学生までの生徒がいます。小学校1年生の子を3年生や4年生の所に一緒に入れることはできないですし、大学生の子を小学生と一緒にやるということはできないので、これは個別になります。
菊田 とても丁寧に個々の状況を見てから授業を始めるのですね。
菊田 ICTの使い方だけではなく学習のやり方については、どんなアドバイスをすることがありますか。
佐藤 テスト勉強で、ちゃんと本質を理解するということよりも、「どういう問題がでるのか?」というパターンを知り、問題と答えのペアをただ暗記をするだけ、それが学習だと思ってしまう子がいますよね。
菊田 いますね。点を取ることが目的の勉強というか、目先の学習というか。
佐藤 でも、「そうじゃないんだよ」と。
テストは単に暗記出来ているかを確認されているのではない。習得した知識について理解ができているかを、こういう形(テスト)で確認をしています。なので極論すれば、テストは点数を取ることよりも、「なんで間違えたんだ」と振り返ることが大切です。そこを先生が正しくナビゲーションできてないような気がするんですね。
ブリキは、生徒の先生の見学を歓迎しているんですよ。ほとんどのお子さんの先生が、学校への配慮のご相談段階ぐらいになると見学にいらっしゃいます。それでご説明をして、「こういうことなのか」という理解をして頂きます。
菊田 それは良いですね。
佐藤 なかには「また来たんだ」というぐらい、しょっちゅう来る先生もいて。
最近一番来られているのが某有名私立中の先生で。ちょうど取材で記者さんも来られたんですが、そしたらその記者の方が「あっ!」とびっくりされたんです。「お知り合いですか?」と聞いたら、「有名な先生だよ」と教えていただきました。ものすごく良い授業されるんですって。
たとえば社会とかで、いろんなものが出てきた時には、全部実物を用意してきて、実物を見て触れる、そういう授業をする先生だそうです。
菊田 そうなんですか。
佐藤 「よく来る先生だな」とは思っていたんですけど。たまたま記者さんがいたので、3人でお話しする機会がありました。すると先生は、「私は出来るだけ子供たちのイメージをふくらませるために、実物を持ち込むとかいろんな授業をやってきたんだけど、学びにくさがあって、そういうことにテクノロジーが使える、ということの見地が全くなかった。なので、これは身につけなければいけないと思いました」とおっしゃっていました。
菊田 素晴らしい先生ですね!「今から変わって頂ければ良い」と私も思っています。今やらない先生の中には、「今までも僕はそういう子たちを見てきましたよ、でも今までの子たちにやって来なかったので、これからもやらない」と言う方もいて……
佐藤 関係ないですよね。
菊田 テクノロジーは昔なかったし、そしてそれを使うことに効果があるという知見が広まってきたから、今変わってくれれば良いな、と思うんですけど。
武井 先生向けの講座みたいなのがあると良いですよね。
佐藤 毎年、夏に魔法のプロジェクトで行っています。
菊田 それは1日何時間とか何日講座とか?
佐藤 午前3時間、午後4時間の計7時間でやっています。
菊田 1日で学べるんですね。
佐藤 はい。毎年夏に1回だけやっています。
菊田 ぜひ私たちからも案内させて頂きたいので、やるときにはぜひお知らせください!
佐藤 ブリキは、「本人に力をつけ、それをどんな風に良い形で使っていけるのか」をアシストしています。けれども、いい使い方をする、というところには、学校や先生の存在が大切になります。ブリキとしてはさっき言ったように、「見学という形で理解をしていただく」ということをできるだけさせて頂いています。
菊田 一度でも見学すると目からうろこだと思います。
さて次回は、「パルステップ」についてお伺いしたいと思います。
佐藤 はい。このアプリは、お子さんと学校を繋いで、不登校や学びにくさから学べていない部分の学習をサポートするアプリなんです。
菊田 やはり学力って大事ですよね。学習面で失った自己肯定感は、学習面で取り返さないと本当の意味で戻らない。しかも無料なんですよね。
次回、ぜひ詳しく教えてください。
次回は、11月20日公開予定です。
★1話目のあるよセレクト『未来につながる、学びの技術を手にする』はこちらからご覧いただけます★
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ