【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
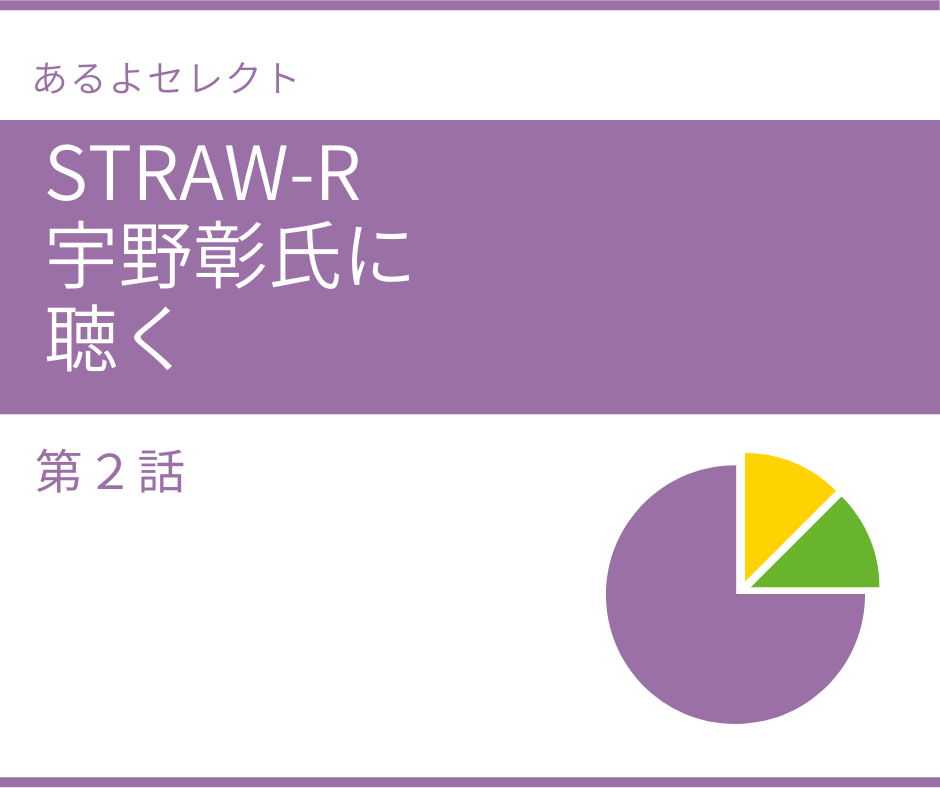
菊田 読字障害の出現頻度というのはどのぐらいなのでしょうか?
宇野先生 発達生読み書き障害(発達生ディスレクシア)の出現頻度は、小学2年生から6年生を対象とした調査では約8%いると報告されています。40人学級に3人ほどいる計算になります。発達性ディスレクシアにおける読みの障害の出現率は、日本人ではひらがなで0.2%、カタカナで1.4%、漢字で6.9%です。
菊田 ちょっと驚くほど高いですよね。
武井 読み書きの習得について、トレーニングは年中・年長で始めるよりも小学校に入ってからの方がいいと前回のお話で伺いました。では、検査はいつ頃したらいいと先生はお考えですか?
宇野先生 就学前に検査して遅れがあるとわかっても、ちゃんとしたトレーニングができるのは小学校に入ってからになります。だから検査も小1のときでいいのかなと思います。
武井 小学校の入学時ということですか?
宇野先生 僕たちが実際に調べたときも、前回お話ししたように、小学校1年生の夏休み前の7月にSTRAW-Rを実施し、夏休み明けの9月にもう一度STRAW-Rをやったら、習得度が上がっていました。だから、そこらへんだと思います。入学後にトレーニングすれば夏休み前後で追いついちゃう。
武井 以前、先生がおっしゃっていたことでたいへん興味深かったのが、入学前の就学時健診時に読み書きの検査をすることで、読み書きに苦手さがある子が集中しないクラス分けをすることができるというお話です。それはいいなと思いました。
宇野先生 前回、話に出たつくば市と取手市の一部で実施されている取り組みのことですね。僕たちの想定通りの検査であれば、就学時健診時に実施するのがいいと思います。就学時健診に取り入れた「ひらがな読み検査」の結果に基づく入学後の取り組みなど、データはたくさんあります。
就学時健診で10個のひらがなを読んでもらって、3字以内しか読めなかった子の中にやっぱり発達性ディスレクシアの子が入っていました。つまり、このスクリーニングは読み書きに困難が出ている子どもを拾うものですが、この検査によって漏らすことなく、発達性ディスレクシアをすくいあげることができました。
菊田 それはやはり行政単位でやることになりますよね。その就学時に行う検査というのは簡単なものなのですか?
宇野先生 就学時健診時に読みの検査を入れること自体は難しいことではないと思います。先生方の負担も少ない。実際、読み書きに問題がある子がいたとしても、早めにわかるので現場の先生方も対応することができますし、関わった先生方からの評判も良いです。
菊田 検査内容はどういったものなのでしょうか?
宇野先生 10個のひらがなの文字を読めるかどうかだけです。時間を計ったりはしない。10個ですから、あっという間です。検査者は、「よくできたね。よくがんばったね!」と言って子どもを帰します。子ども達も読めたかどうかは気にしないみたいです。
菊田 そうやって子どもの状態を把握することができるんですね。しかも、学校で把握することができる。
宇野先生 その学校に進学する予定の子どもたちの検査ですから。
菊田 そういう特性をもったお子さんが入学してくるということを先生方が事前に知ることができる。先生にとっても、子ども本人にとってもすごく意味がありますね。つくば市と取手市の一部での新しい取り組みということですが、うちの地域にも取り入れてほしいです。
武井 この取り組みはいつぐらいから実施されているのですか?
宇野先生 たぶん4年前ぐらいかな。実施した複数の学校で「よかった」というお話でした。
ひとつの学校では完璧に近いぐらいうまくいって、夏休みが終わったとき読み書きの習熟に遅れがある子は1人しかいませんでした。そのお子さんは、お母様が真面目にお教えになったから「うちの子は覚えが悪いのかもしれない」と気づかれて。だけど、特別支援を受けるかどうかの踏ん切りがつかなかった。そういうこと、ありますよね。9月にわかっていたんだけど、なかなか決められなくて。
武井 わかります。
宇野先生 並行して、専門的な教員を養成するため、約30時間のトレーニングを先生方に実施しました。教育委員会から推薦のあった20~30人のうち、合格できるのは5人ぐらいという難しいものです。そのうちの一人の先生がそこの学校にいらして、いつお母様から「お願いします」と依頼されても大丈夫なように、お母様とのコミュニケーションを大切にして勤務していたんですね。なかなか決心がつかないんだなぁと思いながら準備していたら、12月頃、ついに「お願いします」ということになったんです。そこから細かい検査をして、典型的な発達性ディスレクシアだとわかりました。
僕たちのトレーニング法の条件にぴったり合う子だったので、そこからトレーニングを始めたら、4週間で完全に追いついちゃった。ですから、その小学校の当時の1年生は、ひらがなの習得で遅れている子は1人もいなかった。つまり、発達性ディスレクシアの子はいるけれど、習得度としては問題ない。追い付いている。非常にうまくいったケースです。
菊田 大人の気づきと受け止めで、子どもを救ってあげられる。教室で、ひとりで困難に向き合う情けなさから救ってやりたいですよね。
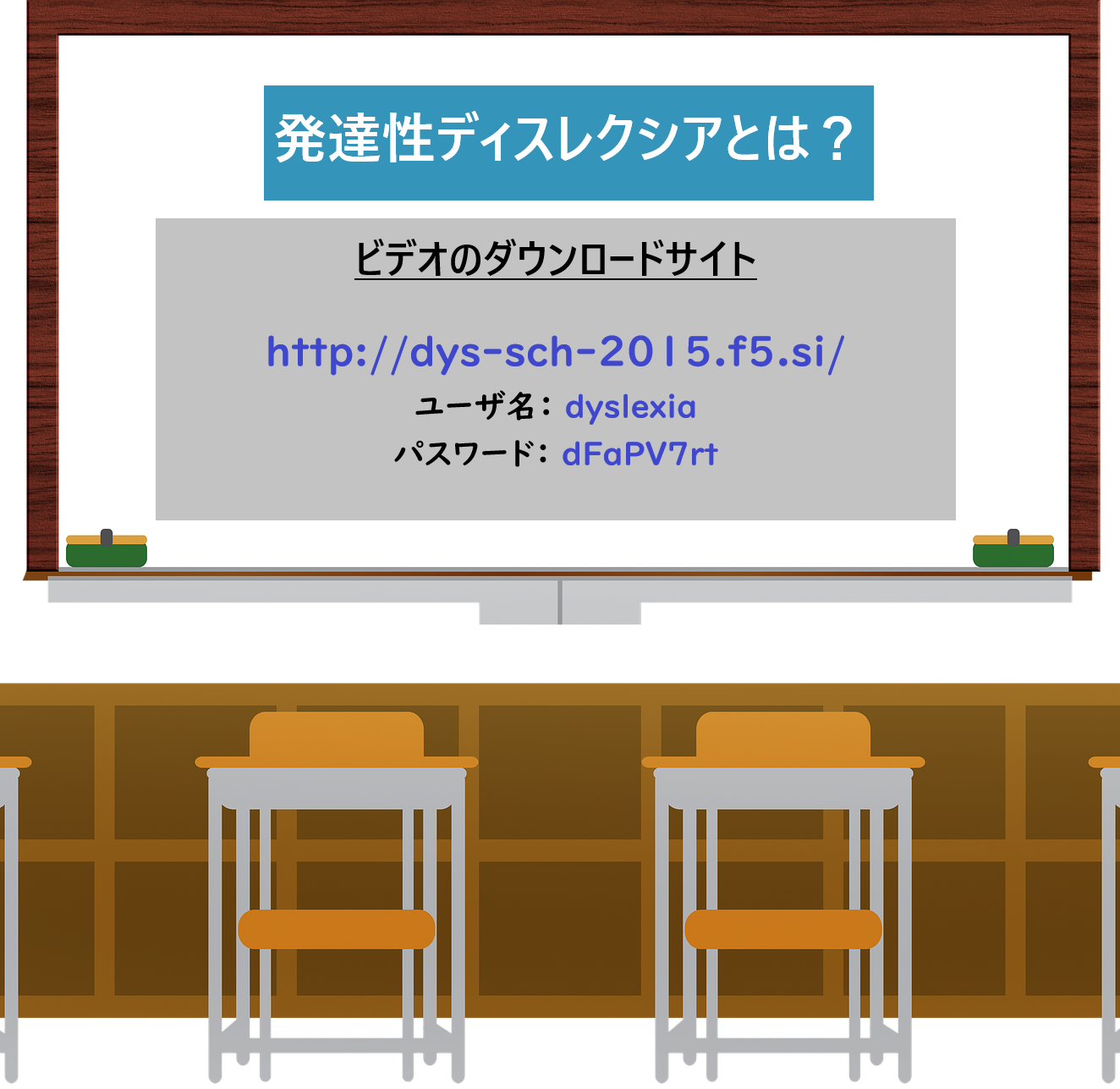
★前回のあるよセレクト『発達性ディスレクシアとの向き合い方』はこちらからご覧いただけます★
次回8月10日公開のあるよセレクトは、あるよ(有料)会員限定です。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ