【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
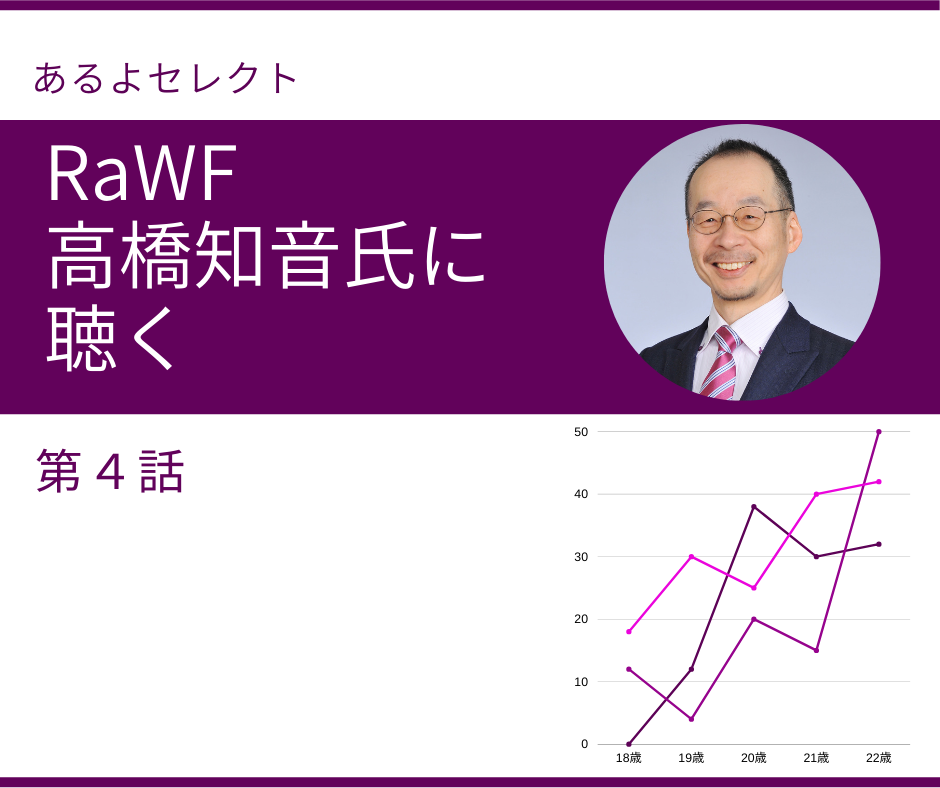
大学生になっても、読み書きの問題だと気づかない
武井 実際に生徒さんが大学に入ってからLDが分かった場合、ご本人に自覚がない状態だと思うんですけれども、具体的にはどんなことで困って、LDへの気づきになったのかをお聞かせいただけますか。
高橋先生 そうですね、まあ本当にLDっていう認識にはならないかもしれないんですけれども、読み書きが困難ということによってうまくいってないということに気付く例でも、最初からそこで相談に来る学生ってあまりいないんですね。私が聞く例としましては、カウンセリングというか、どちらかと言えばメンタル的な問題で相談に来ると。それで、カウンセラーがいろいろ話を聞く中で、実はこのメンタルの問題は、大学の学業がうまくいってないから色々気持ち的にもまいっているんじゃないかと気づき、さらに話を聞いていくと、能力が低いという問題ではなくて、本当に読み書きのレベルで困ってることが、学業の困難につながっているんじゃないかと気づくケースが相当数あるようなんです。私は、学生相談関係の学会や研修会の講師をやったりもするんですが、「読み書きの問題は大学生でもありますよ」という話をすると、そういったカウンセラーの方から、実はこんな相談があるという相談を受けることは結構あります。
菊田 学生を取り巻く誰かが、それも教員にしろ、カウンセラーにしろ、できるだけたくさんの方がLDを知っていてれば、LDの子どもの苦悩を見つけ出してやれるというか、気づけるようになっていくってことですよね。「世の中にはLDっていう困難がありますよ!」ということを伝えていく意義は大きいなと思いますね。
読み書きの困難についての調査
高橋先生 そういったこともあって、読み書きの速さの検査と同時に開発したのが質問紙です。尺度という形で、表面的には『読み書きの困難についての調査』という質問紙なんですけれども、実際にLDのある方の困難経験をもとにつくった質問紙なんです。ただ学習がうまくいかない中でも、背景にそういうLDの可能性もあるということを、質問紙である程度見ていけるようなものになっています。
菊田 それはRaWFの中にあるってことですか?
高橋先生 はい、RaWFと一緒に使えるような形で作った、別の質問尺度です。
菊田・武井 質問紙は良いですね!!
菊田 中学でも高校でも、誰も気づいてくれなくて、自分でも分からないけれど、うまくいかない状態の子って、すごく多いんですけれども、その質問紙がもし使えたら、教員の気づきにもなるし、本人の気づきにもなりますね。「うちの子怠けているんです!頑張りが足りないんです!」っておっしゃる親御さんの気づきにもなっていきますよね。
高橋先生 その一番短い短縮版は、7項目でチェックできるんですけれども、大学の学部の教養の授業でーーこれはさまざまな専門の人が取って、いろんな教員がトピック的に話す授業なんですがーー私は色々な発達障害を紹介し、かつ読み書きの7項目のチェックリストを出しました。そしたら、感想の中で何人かが、「自分もちょっと当てはまっているところがあるかも」というのが出てきましたね。
菊田 その質問紙はもう公開されているんですか?
高橋先生 はい、本と一緒に出す予定です。
菊田・武井 それは楽しみですー!!
菊田 特にその質問紙は、もう少し小さい学年にも使えると考えて大丈夫でしょうか?
高橋先生 はい、質問紙は2種類の項目があって、1つは大学生活の中で困っていること。もう1つは小学校時代どうでしたか?という項目なんです。小学校時代というのは、LDの特徴的な行動のリストなので、そこでたくさん当てはまっていると「あ、そういう傾向があったんだね」っていうのは、かなり掴めるかなと思います。
菊田 それはかなり助かりますよね。小学校の先生方が、その質問紙さえ知っていてくだされば、「この子もしかしてそうかもしれない」という、気づきに繋がっていくかもしれない。
武井 大学の学生支援室とかで当たり前のように広がれば、そうやって発達障害の子たちも救い出せると思うんですよね。
高橋先生 そうですね。それを目指しています。
だから、非常に短い7項目でチェックできるというのも、お手軽にとりあえず楽しくやってみることで、まずはとっかかりと言いますか。
菊田 LDという診断がなくても、その質問紙が根拠になって、支援に繋がっていくと考えても大丈夫ってことですよね。
高橋先生 質問紙だけ、というわけにはいかないとは思います。ただ質問紙で高得点だった場合に、「あれ、大丈夫?」ということから始まって、「じゃあRaWFやってみよう」となって、「あ、やっぱり遅いね」となれば、配慮には結びついていくかなと思います。そういう風になることを狙っているんですけど。
菊田・武井 はぁ~!わぁ~!すごい!期待が持てる。
菊田 はっきりするというか、とにかく根拠が欲しいけど、根拠がないっていうのが今までの悩みでしたので・・・。しかも手軽にできるところがいいし。なんというか、LDだったら一生終わりみたいに考える親御さんって本当に多いんだけど、いやそうではなくて、発想が面白い子達なんだから、読み書きをカバーしてやれば、「もっといけるよ!」と子供を応援してあげることもできるし、勇気づけてあげることもできます。RaWFが存在しているというだけでも、世の中にパッと光が差す感じがしますよね。
高橋先生 そういっていただけると、はい。
武井 ぜひ、うちの子の大学でも使ってもらいたい。
菊田 知的好奇心が強いけれども読み書きにつまずいている子供たちの自己肯定感を支え育てていくには、学びを続けていける可能性があるっていうことはすごく大きいんです。小学生を育てていて、でもこのままだと、大学までは繋がらないんじゃないか、と親は弱気になりがちです。学ぶ能力も意欲もある子供たちが、望んでも大学に進学するまでの学びを続けられないとしたら、その挫折によって失う自己肯定感をどんな形で取り戻してやることができるのか、親は途方に暮れてしまうんです。こんなに手軽に検査ができて、これさえ満たせば、「はい!支援」という風になるのであれば、親も子も「がんばれる」っていう、きっとそういう兆しになると思います。
***=====***=====***
次回は、12月1日 会員限定公開です。
会員様は「あるよストーリーバンク」にログインして「あるよセレクト」からお読みください。
どうぞお楽しみに。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ