【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ
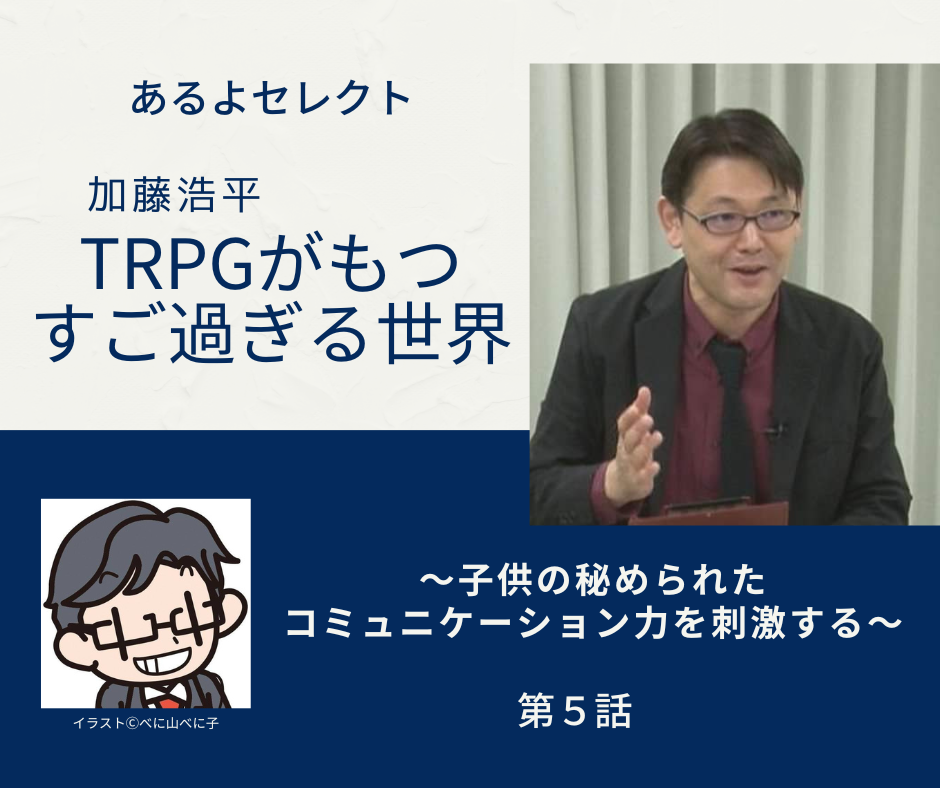
前回のつづき・・・・・
TRPGはルールという「枠組み」があるからこそ、想像力が生まれる効果がある。偶然生まれるユニークさや子どもたちが思いつくユニークさが、どんどん連関して広がっていくところが面白い。想定外が生む相乗効果。
子どもが自分の役割を感じることの変化
加藤:そうです。僕は、周りの参加者を傷つけたり(もしくは過度に不快にさせたり)あと著しくゲームバランスを崩したりするものでなければ、子どもたちの提案や発想は物語の中に取り入れるようにしています。ゲームマスターとしては、できるだけ「それはできない」「それはダメだ」を言わないようにしています。そうしてTRPGをやってきた結果として、生まれた言葉(フレーズ)が「そうきたかー!」だったところもあります(笑)。
菊田:加藤さんのその声掛けで、「受け入れてもらっている」「喜んでもらっている」ということを感じられる。子供たちは「自己有用感」みたいなものを感じている気がします。
加藤:「そうきたか~! …でもこの話の展開、どうするかなぁ? どうしたらいいかな?」って僕も素直に悩んでいることを開示する時があります。そこまで物語の展開を事前準備していなかったり、本当に想定外のことが出てきたときには「どうしようかね?」と子どもたちと話し合って「それはちょっと難しいかな」「それもちょっと無理があるなぁ…」「あ!それだ!そのネタいただき!」みたいな感じでやっていますね。
菊田:子どもたちと一緒に作り上げていくってことですね。
加藤:冒険の中継地点になる街の名前をどうするか、急きょ出す必要が出てきた登場人物の名前をどうするか…に始まり、プレイヤーからの思わぬ提案をどう扱っていくかも含めて、共同制作ですね。なかなか体力を使いますが、子どもたちからは「あの時のあの物語のシーンが楽しかった」とか「あの時のあのキャラクターの発言が面白かった」とか「あの子が話す内容は面白いから話すのを待って聞こう」といった発言というか感想ももらえます。
そんな中で、子どもたちも変化していきます。これは、僕のTRPGに参加したASDのあるお子さんのエピソードなんですが、その子はプレイ中にゲームとは全然関係ないことを言って、周囲からも「ちゃんとやれよ」みたいなことを言われてしまうような、ちょっと反抗的な子だったんです。初回も「親に言われて(仕方なく)来た」とぶっきらぼうでした。でも、ゲームをやっていく中で、たまたまその子の発言の中に「この物語を展開させていくのにすごくいいアイデアじゃないか!」というものがあったんですね。他の子たちからも「それ、いいね!」と高評価でした。そうしたら、それ以降その子は「別にこのゲーム楽しんでませんけど…」という顔をしながら、たまにボソッ、ボソッとアイディアを出していくようになった。そのうちに「いいね!」「それいいね!」とみんなが反応するようになって、気づいたら、その子は、そのチームの中のアイデアマンというか参謀役みたいな立場になっていました。
後日、調査研究の中でその彼にインタビューをしたら、「最初は活動を茶化していたけれど、そういう立場(参謀役)になったことによって、だんだんみんなと話ができるようになっていた」と言っていました。喋りながらはにかむ様子が印象的でした。
別に集団や活動に適応してもらうことは僕の目的ではないです。ですが、他の子にとって「その子がいてくれると助かる」「その子がいると楽しい」という存在になっていた。それに対して、彼自身もそこで自分の役割を感じて行動するようになっていたという、大きな変化だったのかなと思っています。
菊田:役割が居場所を作っていくっていうのはありますね。そしてそれがゲームの中だけではなく、現実世界にも影響していって、役割を自分で感じることで、ここに「自分の居場所がある」という実感をもつことができるようになっていく気がするんですよね。
加藤:それはそうだと思います。参加している子どもたちが自分の「役割(ロール)」を楽しめる、その「役割」に対してポジティブに捉えられることは、その子たちの成長にもつながっていると思います。
菊田:役割に対してポジティブになるっていうことは、その集団に対してポジティブになれるっていうことですよね。
加藤:そうですね。TRPGを通して「役割」を楽しむ中で、別の場所でも「自分に向いている役割ってなんだろう」ってことを学んだ子もいます。これもまたあるASDのお子さんのエピソードですが、彼は学校の部活動で一生懸命主導的にやっているのに逆に浮いてしまって、周囲とうまくいかなくて悩んでいました。けれども、TRPGの中で仲間をサポートするキャラクターを担当したことから、部活動でも自分が無理に主導するのではなくて、サポートする側に回ることで活躍する方法があることに気付いたそうです。「そうか、自分が仕切ろうとして必死になるんじゃなくて、誰かのサポートについて活躍するっていう立場もあるんだ」ということを学んだ、と言っていました。その後は部活動での人間関係も良くなって、本人も悩む事がなくなったということでした。
菊田:それは、訓練やトレーニングではなく、自発的に、自主的に、学んで習得していくってことですよね。
加藤:そうですね。それが「身になっていく」ってことなんでしょうね。
自分らしさを肯定する
菊田:私は、知的に高い発達障害の子ども達への支援が手薄だと日頃から感じているんですが、そういうところにTRPGは合っているなと思うんです。クリエイティブなところもそうだし、自分で習得していくところもそうだし。
加藤:自分らしい服を自分で選んで着る感じでしょうか。他の人に「みんなが着ているからこれを着なさい」「これが正しいからこれを着なさい」と言われたものを着るんじゃなくて、自分の体へのフィット感とか、身長とか、自分の好きなスタイルとか……つまりそれはコミュニケーションのスタイルだと思いますが、そのスタイルに合った服を着こなすことができるようなものだと思っています。それは、実際にTRPGの中で言葉を“動かす”というか、自分に合ったコミュニケーションの仕方を“肯定できる”ってことなんですね。
例えば、TRPGの中で、全然しゃべれない子がいてもいいんですよ。実際に殆ほとんどしゃべらない子に何人も出会ってきました。でもその子たちはTRPGでは役立たずな存在では決してなくて、キャラクターとしてすごく活躍をしているんです。では、その子がその後、饒舌にしゃべれるようになったかというと、全然そんなことはなかったりします。でも、自分なりに得意な方法を模索して、編み出していって、ちょっとした一言に面白いことを言うとか、自分なりのコミュニケーションスタイルを確立していっているところはありますね。
菊田:言語によらないコミュニケーションでもありますよね。
加藤:そうですね。TRPGのキャラクターシートにイラストを描いて、他の子たちに「すげー。かっこいい!」と言われて、実際に絵を描くことがコミュニケーション手段になっていた子もいます。自分から発信するコミュニケーション。自分が楽な方法で相手に発信する、自分らしい方法で表現をする。その子の場合なら「絵で話しかける」。相手が話してきたことを受けて、しっかりボールを投げ返す。要するに、人の話を聞いてアクションするってことですよね。
菊田:へぇ。それを自発的に学んで行くのね。自発的な成長を促すっていうのかな、TRPGが育むものは本当に面白いと感じますね。
加藤:TRPGはコミュニケーション(やり取り)を楽しむゲームなので、相互のコミュニケーションがないと話が進まないですよね。他の参加者とのやり取りを無視して勝手に話していても物語が進まないので面白くない。だから、インタラクション(相互作用)は結果として起きてくる。しかもそれが楽しい。そしてその楽しさは、演劇の台本の筋書き通りのものではなく偶然性や意外性も加わる。誰かの思わぬ発言や振ったサイコロの思わぬ結果によって、急展開したりするわけです。正解ではない発言をしてそこで会話が切断されるのではなく、むしろ拡張したりもするんですね。みんなが「そうきたか!」という思いになる体験も生まれる。猛獣にさらわれたお姫様を助ける話だったはずなのに、いつの間にか猛獣と恋愛関係になったお姫様の駆け落ちを手伝う話になっていたとかね(笑)。山に住む悪い竜を倒しに行く話だったのに、竜と話しているうちに「竜の言うことも一理あるよな」とか竜に共感する子も出て来て、「これちょっとどうしようか?」「何か良い落としどころはないかな?」みたいな話し合いになるとかね。そんなのしょっちゅうです。毎回「そうきたか!」「そうくるか!」と、どんどん世界が広がっていく。僕自身の世界も広がっていきますし、同時に子どもたちの世界のほうも広がっていているように思います。
以前、読み書き配慮でTRPGをやらせてもらった時に、参加していた子の一人が遊んでいたTRPGの「追加ルール」を思いついて、Wordで打って作って持ってきたことがありましたね。TRPGに刺激を受けて、その子自身の世界が広がっていったんだと思います。その子はTRPGに出会わなければ、自分が考えたものを作って、人に見てもらうということはなかったかもしれません。そのアイディアが素晴らしいというよりは、それを作ってゲームマスターや他の参加者の子たちに見せてくるというアクションがすごいと思うんです。
菊田:たくさんルールを考えてきてくれましたよね。嬉々として見せてくれてね。
加藤:一種のプレゼン行為でもありますからね。その子にとっても初めての体験だったかもしれませんが、それによって世界が広がったんじゃないかと思います。
***=====***=====***
【予告】
次回は、7月15日公開です。
【お問い合わせ先】
一般社団法人読み書き配慮
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-14-4毎日新聞社早稲田別館5階
あるよ相談についてお問い合わせ
その他サービスのお問い合わせ